
もうひとつのノモの国、展示エリア「大地」を知る〜菌の力で空間をつくる「センサリードーム(菌糸パネル)」編〜
パナソニックグループが大阪・関西万博に出展するパビリオン「ノモの国」において、子どもたちの内なる力を解き放つ “Unlockエリア”と対をなすのが、5つのユニークな技術展示を行う“大地エリア”です。ひとの営み、自然の営みが響き合い、それぞれが持つ360°の循環がめぐり合って生まれる「720°の循環」を表現することが、大地エリアのコンセプト。このシリーズでは大地エリアに登場する技術と、展示の実現に向けて奮闘する人々の想いを紹介します。

空間と人との関係値を深める、「自然の質感」という刺激。

原:人の五感を優しく刺激し、感覚をリセットして癒しをもたらしたり、逆に眠っていた感覚を呼び起こすような体験を生み出したりするセンサリードーム。三浦さんは万博に向けたプロジェクトが立ち上がる前から、共通の考えをもった「センサリールーム(https://makenew.panasonic.jp/magazine/articles/065/)」の実現にも取り組まれてきましたよね?
三浦:そうですね。センサリールームとは元々「障害のある人や感覚過敏の方などが落ち着ける空間」として生まれました。パナソニックではその考え方を、「より多くの人に安らぎやリセットの時間を提供できる空間」として拡張。当社が持っている照明や音響技術を生かして、あるがままの自分に向き合える空間づくりに挑戦してきました。
原:大地における「センサリードーム」は、三浦さんが長年取り組まれてきたセンサリールームの考え方を生かした展示ですが、「菌糸パネルを用いる」というところが大きく異なる点だと思います。このアイディアは、どのようにして生まれたのでしょうか?
三浦:人が心地よいと感じる光や音を照明や音響デバイスで演出するだけでなく、「本物の自然」を空間に取り込んでみてはどうだろう、と思ったことがきっかけです。自然な素材、生きている素材で空間をつくり、訪れた人に見て、ふれて、匂いをかいでもらう。そうすることで、より多くの感覚を刺激できるんじゃないかという期待がありました。そこで、元々つながりがあったBIOTAさんに「菌糸を使ってなにかできないか」と相談を持ちかけたんです。

伊藤:私たちBIOTAは、環境中の微生物の多様性やバランスをゲノム解析し、その多様性を高めることで、例えば感染症を減らしたり、人の免疫を高めたりするような社会のデザインに取り組んでいる会社です。その中で「菌糸」というものにも着目していて、これまでにも菌糸を使ったものづくりに何度か挑戦していました。ただ、空間づくりに菌糸を用いる、というのは初めてで。お話をいただいた時は、自分たちに何ができるだろう、どういう形であればBIOTAが参加する意味があるだろう、ということを社内でもかなり議論しました。
原:そうして出た答えが、「菌糸パネル」だったと。
伊藤:これまで私たちが経験していたのは、菌糸を使ったオブジェづくりなど、アートの領域を出ていなかったんです。だからこそ大地では、人の営みの中に菌糸が紛れ込む、より社会実装に近い状態を作りたいと思いました。そこで、菌糸を用いた三角形のパネルを開発し、それをドームの壁に建材として使ってみようというお話をいただきました。
試作・量産フェーズでめざしたのは、社会実装を見据えたクオリティ。

伊藤:菌糸を建材として成立させる、というのは私たちにとっても初めてのチャレンジ。施工に至った完成版を生み出すまでには、多くの苦労がありました。初期の試作の際には、慶應義塾大学の後輩で菌糸建築に取り組むTelostektsチームにもご協力いただきました。このあたりはぜひ、パネルの開発・デザインを担当した田中さんと、量産にご協力いただいた平田さんにお話いただきたいと思います。
田中:最初にハードルとなったのは、パネルの大きさでした。これほど広い面積を菌糸で均質に覆うものづくりには取り組んだことがなくて。三角形の木枠の中で菌糸を成長させ、全体を均質に覆えるようにすることがゴールだったのですが、当初は菌糸が十分に成長しなかったり、板から剥がれてしまったり、乾燥して割れてしまったり、と多くの課題を抱えていました。
三浦:何回くらい、試作を繰り返されたんでしょうか?
田中:大小含め30回以上はトライアンドエラーを重ねましたね。菌糸が剥がれないように木枠にやすりがけをして定着性を上げたり、育てる温度や湿度を変えてみたり……。
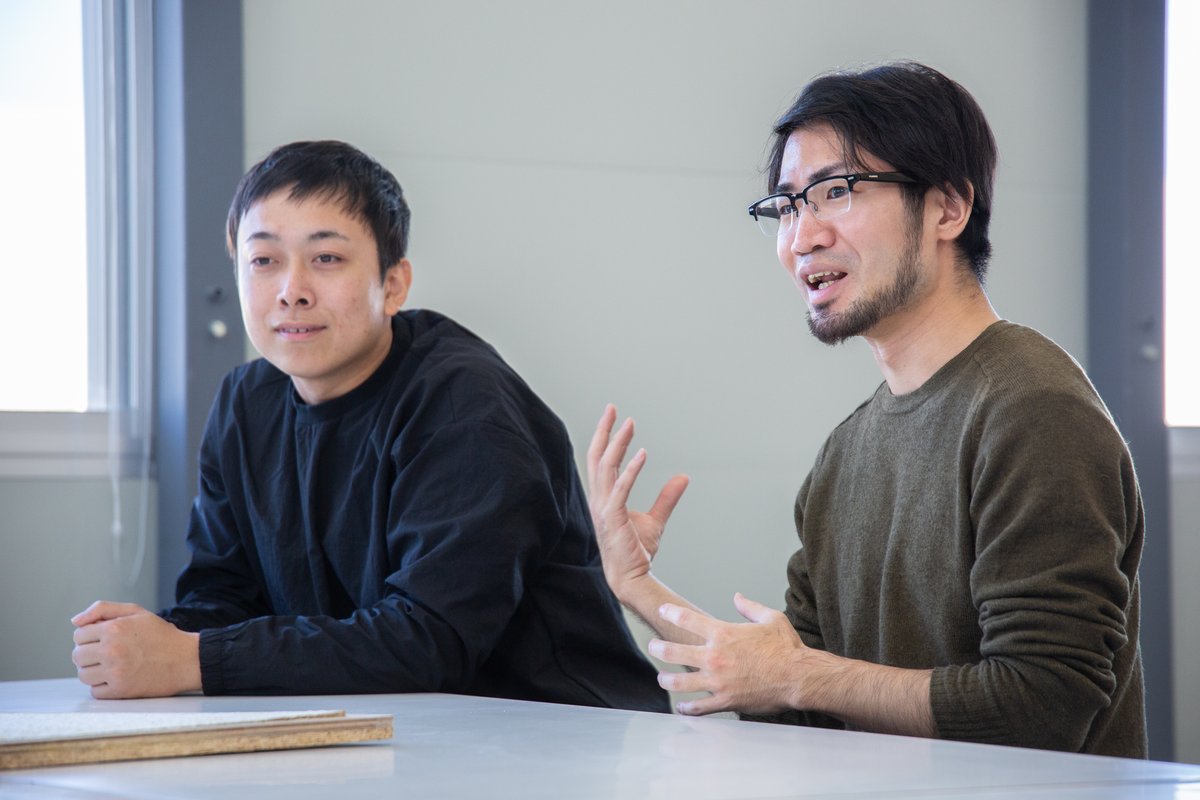
原:いただいた試作品に対しては、長年ものづくりに取り組んできたパナソニックとして、厳しいフィードバックも出させていただいていました。難しいことをお願いしているということは分かっていたのですが、菌糸パネルを建材として機能させる、という日本でも例を見ない取り組みを高いレベルで完成させるために、絶対に手を抜けない、という意識があったんです。
伊藤:製品として守らなければいけないライン、完成度などのゴールは、私たちにも見えていない部分だったので。住宅建築や建材開発のノウハウを持っていらっしゃるパナソニックさんから率直な意見をいただけることが、むしろありがたかったです。
原:ただ単に、展示として菌糸パネルを使ってみました、ということで終わりにしたくなかったんですよね。その先にある事業化や、菌糸パネルが建材として使えるという最初の事例づくりという目線を持ってこのプロジェクトに取り組むのが、ある意味私たちパナソニックが果たすべき責任だなと感じていました。
伊藤:キャッチボールの末に、均一に菌糸に覆われたパネルが出来上がった時は、本当に嬉しかったですよね。
原:「これ大丈夫かな?」「完成するかな?」とドキドキするような状態から、お互いの知恵を出し合って、努力を重ねる。それを繰り返すことで、ある日「いいじゃん!」と全員が納得できる、突き抜けたクオリティのものが完成する。この瞬間こそが、組織を超えた共創活動を行う醍醐味だと感じています。

平田:私たちは完成版の試作品ができあがった時点で、量産を行うというバトンを受け取りました。月夜野きのこ園は普段、食用キノコを育てるための菌床を作っている会社です。弊社の社長から「菌糸パネルの量産」という特命がくだった時は、正直驚きました。菌糸=キノコの土台というイメージしか持っておらず、建材として使うという発想は私たちの中にまったくなかったんです。
三浦:パネルを100枚作っていく、という量産フェーズにおいては、どのようなことが最も大変だったのでしょうか?
平田:木枠の中にムラなく菌糸を育てるにあたって、乾燥と湿潤のバランスに最も悩まされましたね。乾燥させ過ぎてしまうと菌糸が縮んで割れてしまう。一方で、湿度をあげすぎるとカビが生えてしまうんです。
田中:カビを抑制する薬剤を塗布した上で、パネルを一枚一枚カバーで覆って乾燥と雑菌の侵入から守るなど、かなり手をかけていただきました。
平田:本当に、一筋縄ではいかない作業でした(笑)。ただパネル作りに奮闘しながら、改めて「自然の力はすごいな」と感じられる瞬間があって。菌糸を育てるにあたって、カビが生えないように防止剤をかけていたんですが、それでも気づいたらカビが生えているんですね。困りながらも、菌や微生物の「生きようとする力」の強さを感じました。

伊藤:生き物を相手にするからこそ感じられる、難しさとおもしろさがありましたよね。
田中:苦労も多かったですが、菌の力を社会にダイレクトに生かす「菌糸の建材利用」のために試行錯誤をできたことが、今回のプロジェクトの何よりの成果。万博という場で長期間多くの人に晒されることで、今は見えていない課題も出てくるかと思います。でも、それらは全て菌糸を社会実装していくにあたって、いつかは必ず乗り越えていかないといけない壁。社会実装に向けた大きな一歩を目の当たりにできることに、ワクワクしています。
伊藤:菌糸って、本当に建材として大きな可能性を秘めている素材なんです。単位重量あたりの強度はレンガより高いといわれていたり、撥水性や耐火性もあり、生分解性で土に還すこともできる。そんな素材で実際に建物を作ってみるという試みは、世界でもまだあまり例がありません。この展示を通じて、世界に対して発信できるようなエビデンスを生み出していきたいですね。

展示を通して、子どもたちの感覚と自然素材の可能性を開いていく。
三浦:3社が力を合わせ、実現した菌糸パネル。施工された様子を見ていかがでしたか?
伊藤:ドームに入ると菌糸独特に匂いも感じられましたし、ひとつとして同じ色味、質感がないパネルの自然な風合いによって、求めていた空間が出来上がりそうだという予感がしました。
原:試作の段階から、「どこまで均一なものにするか」という点は重要な議論のポイントだったんです。突き詰めれば、真っ白で真っ平な菌糸パネルも実現できたかもしれませんが、そうなってくるとパネルが菌糸でできている意味が失われてしまうよね、と。
伊藤:そうですよね。パネルごとの微妙な色味の違いや、菌糸ならではのふわふわとした凹凸感を失わないような基準を採用したことで、「本物の自然」を感じられる仕上がりになったなと思います。

三浦:そうやって生み出した自然の風合いから、訪れた人たち、特に子どもたちが何を受け取ってくれるのかが楽しみです。本当に現代って、目の前にあふれているデジタルな情報の中から、自分に必要なものを必死に選び取って生きている、という感覚があって。センサリードームではそういった情報を一度リセットして、手触りとか匂いとか、人が本来持っている感覚を使って何かを得てもらい、元気をチャージしてほしいです。
伊藤:私は自然というものが、実は一番情報量が多い刺激なんじゃないかと思っていて。不規則だったり、不鮮明だったり、いい意味でのノイズが自然界にはあふれています。センサリードームは、そういったデジタルとは違う情報量の多さを、感覚で処理する経験をしてもらえる場所。訪れることで子どもたちの感覚が開いていって、日常に戻った時にいつも歩いている道、街の見え方が少しでも変わってくれると、嬉しいですね。
原:私たちの世代が子どもの頃って、祖父母の家なんかに行くと、土壁や畳などたくさんの自然素材と家の中でふれあえていたと思うんですね。時代の変化とともにそういう素材は、少しずつ住宅から無くなっていく方向にあります。でも菌糸パネルというプロダクトが生まれ、実用化されることで、自然素材の力が新たな解釈を帯びて生活の中に舞い戻ってくる。日本の住宅や建材をつくってきたパナソニックに身を置くからこそ、この展示がそんな変化のきっかけにもなれば、と考えています。


